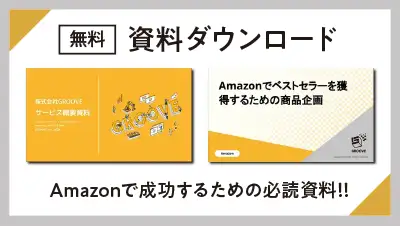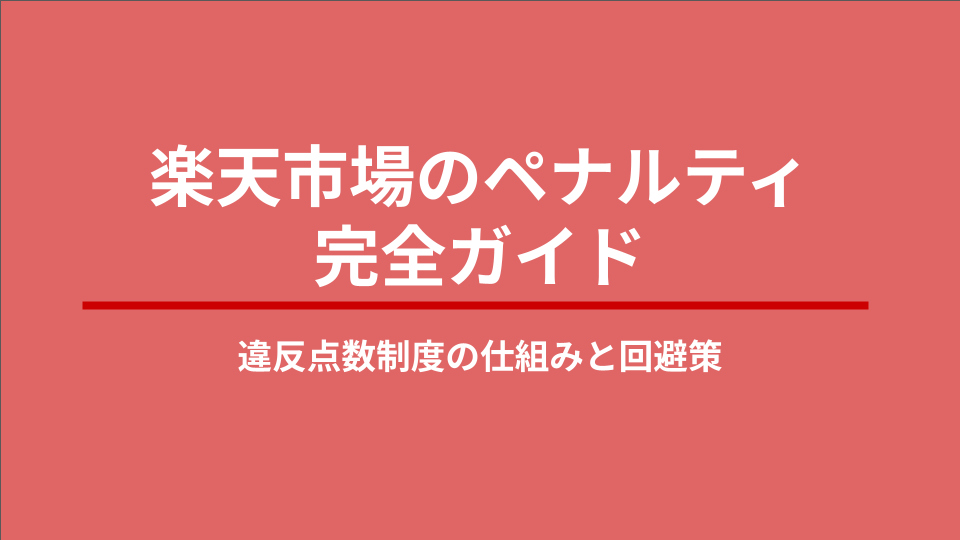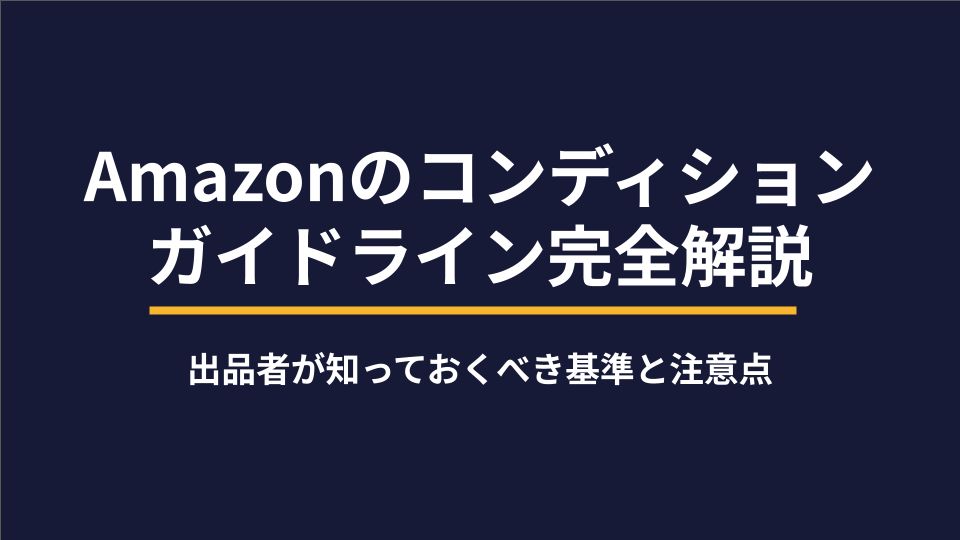Amazonセラーとベンダーという二つの出品形態の違いとそれぞれで必要になる施策
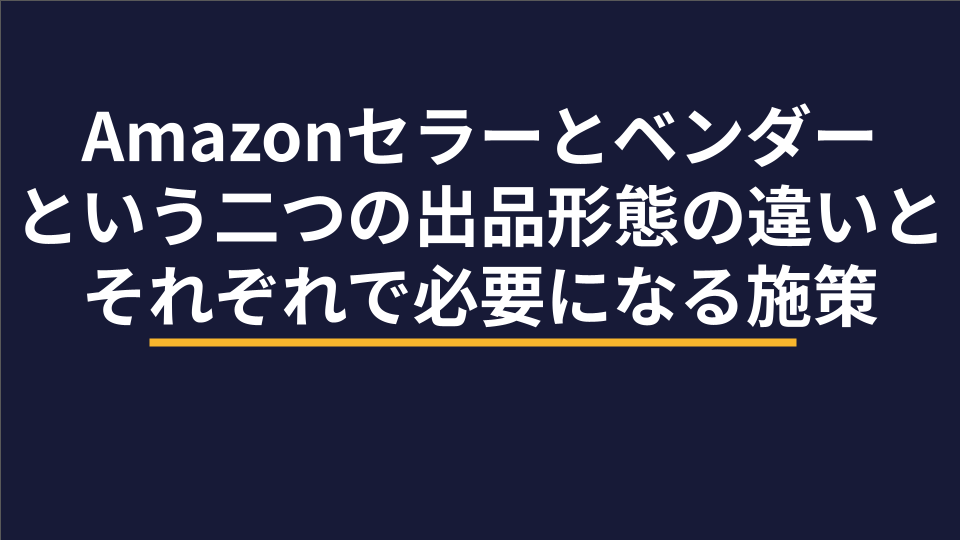
Amazon出品を検討するメーカーにとって、「セラー」と「ベンダー」という二つの出品形態の選択は事業戦略に大きく影響します。それぞれ異なる特徴とメリット・デメリットがあり、求められる施策も大きく異なります。本記事では、両者の違いを詳細に解説し、成功に必要な具体的施策をご紹介します。
目次
1. セラーとベンダーの基本的な違い
2. 料金体系と参入条件の比較
3. セラー出品のメリット・デメリットと必要施策
4. ベンダー出品のメリット・デメリットと必要施策
5. 選択の判断基準と実践的な考え方
6. 成功に向けた戦略的アプローチ
1. セラーとベンダーの基本的な違い
Amazonの出品形態は「セラー(Seller Central)」と「ベンダー(Vendor Central)」に大別されます。この二つの最も大きな違いは、誰が商品を販売するかという点にあります。
セラーの特徴
セラーは、Amazon.co.jpに出品者として登録し、自社の商品を自ら出品・販売する形態です。商品ページには出品者名が表示され、価格設定から在庫管理、発送まで、販売に関わる業務を自社で管理します。個人事業主から大企業まで、幅広い規模の事業者が利用しており、Amazonマーケットプレイスの主要な構成要素となっています。
FBA(Fulfillment by Amazon)を利用することで、商品の保管、梱包、発送、カスタマーサービスをAmazonに委託することも可能です。これにより、セラーは物流業務の負担を軽減し、ビジネスの拡大に専念できます。
ベンダーの特徴
ベンダーはAmazonと直接取引を行う卸売業者として位置づけられます。ベンダーはAmazonに商品を卸売りし、その後の販売はAmazonが担当します。商品詳細画面には「Amazon.co.jp」が販売元として表示され、顧客にとってはAmazonから直接購入している形となります。
この販売形態の違いにより、管理する業務範囲や責任の所在、収益構造が大きく変わってきます。セラーは直接販売による高い自由度を得られる反面、販売に関わる全業務を自社で担う必要があります。ベンダーは販売業務をAmazonに委ねることで運用負荷を軽減できますが、価格設定や販売戦略をコントロールできません。
2. 料金体系と参入条件の比較
セラーとベンダーでは、コスト構造と参入条件が大きく異なります。これらの違いを理解することは、事業計画策定において極めて重要です。
セラーの料金体系
セラーには大口出品と小口出品の二つのプランがあります。大口出品では月額4,900円の固定費に加えて、商品カテゴリごとに8-15%程度の販売手数料が発生します。小口出品は月額費用無料ですが、商品ごとに100円の成約料と販売手数料がかかります。
さらに、FBAを利用する場合は別途手数料が必要となり、広告運用を行う際は広告費も発生します。これらの費用は全て販売実績に連動するため、売上が上がるほどコストも増加する構造になっています。
ベンダーの料金体系
ベンダーには月額利用料や販売手数料は発生しません。しかし、Amazonへの卸売価格は定価の40-70%程度となることが一般的で、セラーと比較して1商品あたりの利益率は低くなる傾向があります。
参入条件の違い
セラーは基本的に誰でも登録可能です。必要な書類を準備し、アカウント審査を通過すれば出品を開始できます。一方、ベンダーはAmazonからの招待制となっており、一定の販売実績や供給能力を持つ企業のみが利用できます。最低でも年間1億円程度の売上がベンダーマネージャーとの交渉の基準とされ、家電などの大きなカテゴリーでは年間10億円以上の売上が必要になることもあります。
3. セラー出品のメリット・デメリットと必要施策
セラー出品のメリット
主体的な販促活動の実現
セラー出品の最大のメリットは、販売における高い自由度です。商品の価格設定を自由に行えるため、市場の需要動向や競合状況に応じて柔軟に対応できます。広告キャンペーンの作成や管理ができ、ターゲットオーディエンスに対するプロモーションを実施することで、製品の認知度や売上を向上させることができます。
商品の保管・発送委託の選択肢
FBAを利用することで、商品の保管や発送をAmazonに任せることができ、発送業務の手間を省くことが可能です。FBAを利用するセラーの商品はAmazonプライムの対象となるため、プライム会員向けの迅速な配送サービスを提供でき、販売機会が増える可能性があります。
価格設定の完全な管理権
商品の販売状況や競合の価格、目指す利益などに応じて、販売価格を自由に決めることができます。価格の自動調整ツールを使用して、特定の条件に基づいて価格を自動的に変更することも可能です。
セラー出品のデメリット
消費者の信頼獲得までの時間
セラー出品では販売元が自社のショップ名として表示されるため、Amazonブランドの表示がされません。新しいセラーが市場に参入する際には、既存の大手セラーや高評価のセラーと競争することになり、消費者の信頼を得るまでに時間がかかります。
利用手数料の負担
大口出品の場合は月額登録料に加えて販売ごとに成約手数料がかかります。また、在庫管理や配送、カスタマーサービスなど、多くの業務を自社で行う必要があるため、運用コストや業務の負担が増える可能性があります。
激しい競争環境
セラー出品では参入が容易なため、既存の大手セラーや高評価のセラーも多く、効果的に差別化できていないと価格競争に巻き込まれる可能性が高くなります。
セラー出品で必要な施策
商品ページ最適化
商品タイトル、商品説明、画像の品質向上は売上に直結します。検索キーワードを適切に配置し、顧客の購買意欲を高める魅力的なコンテンツ作成が重要です。
広告運用戦略
Amazon内の各種広告メニューを効果的に活用し、商品の露出を高める必要があります。スポンサープロダクト広告、スポンサーブランド広告、スポンサーディスプレイ広告を使い分け、ROIを最大化する運用が求められます。
価格戦略と在庫管理
競合分析に基づく適切な価格設定と、売り切れを防ぐ在庫管理が重要です。価格自動設定ツールの活用も検討すべき施策の一つです。
レビュー対策
高評価レビューの獲得と低評価レビューへの適切な対応により、商品の信頼性を高める必要があります。
SEO対策
Amazon内検索での上位表示を狙い、商品タイトルや説明文にターゲットキーワードを自然に組み込む施策が必要です。
4. ベンダー出品のメリット・デメリットと必要施策
ベンダー出品のメリット
消費者の信頼獲得
ベンダー出品では、商品詳細ページの販売元に「Amazon.co.jp」と表示されます。これにより、ユーザーに対して販売者であるAmazonが商品の品質を保証しているという安心感を与えることができます。Amazonの厳格な品質管理基準を満たしていることも保証されるため、消費者は安心して商品を購入することができます。
カートボックス獲得率の向上
Amazonでは「相乗り出品」が採用され、1つの商品に対して商品詳細ページは1つというルールが存在します。カートボックスの獲得とは、ある商品の商品ページのトップに自店舗の商品が掲載されている状態を指します。ベンダー出品はセラー出品よりもカートボックスを獲得しやすいといわれており、これはAmazonが価格を設定し、費用対効果の高い価格として判断されやすいためです。
招待制による競合の少なさ
ベンダー出品に参入するためには、Amazonからの招待が必須条件となります。参入障壁が非常に高く、セラー出品とは違い料金を払えば参入できるプログラムではありません。そのため、セラー出品と比較してライバルが少ないことが魅力となります。

ベンダー出品のデメリット
価格設定の制限
販売のすべてをAmazonに委ねることになるため、Amazonでの販売価格を出品者が決めることができません。Amazon側の需要予測によっては販売価格が頻繁に変動することがあり、他の販売チャネルとの価格統一が難しくなります。
主体的な販促の制限
ベンダー出品はAmazonの販売に委ねる形態であるため、販促のコントロールを能動的にできなくなります。売上が伸びていない状態でも、出品者自らが販売価格の見直しやセールの実施をすることができません。
在庫管理の困難さ
ベンダー出品ではAmazonの注文書作成の基準が厳しいため、在庫管理を適切に行うことが難しい傾向にあります。Amazonの発注量やタイミングが予測しにくく、在庫過多や在庫不足に陥るリスクがあります。
ベンダー出品で必要な施策
安定供給体制の構築
Amazonからの発注に迅速に対応できる生産・物流体制の整備が最重要課題です。POに対する迅速な対応により、Amazonとの信頼関係を構築する必要があります。
在庫管理の高度化
在庫管理の課題に対応するため、以下の対策が有効です:
- データ分析ツールの活用:過去の発注データや販売トレンドを分析し、需要予測の精度を高める
- フレキシブルなサプライチェーンの構築:短期間での在庫補充が可能な体制を整備し、複数のサプライヤーと契約
- 安全在庫の設定:不測の需要増加に対応できるよう適切な安全在庫を設定
- 管理システムの導入:在庫管理システムや自動発注システムの導入により効率化を図る
売上実績の維持・向上
継続的な発注を確保するため、広告運用や商品ページ改善により売上実績を維持する施策が重要です。
Amazonとの関係構築
担当者との良好なコミュニケーションを通じて、マーケティング支援や新商品投入の機会を獲得する必要があります。
請求処理の確実な実行
ベンダーは自ら請求書を発行する必要があり、出荷月の翌月第5営業日までという期限を厳守する必要があります。
5. 選択の判断基準と実践的な考え方
セラーとベンダーのどちらを選択するかは、以下の3つの判断基準を総合的に検討することが重要です。
利益性の比較
掛け率や手数料の観点でどちらの方が販売者にとって利益を出すことができるかという考え方が重要です。ベンダー出品ではAmazonが商品を仕入れ、その後販売価格を設定します。これにより、ある程度の収益は保証されますが、利益率はAmazonの交渉力に依存します。一方、セラー出品では自分で価格設定ができるので、手数料を考慮しても、高い利益率を得られる可能性があります。
運営のしやすさ
業務の分担や負担がどのくらいなのか、マーケティング施策や商品ページ作成、広告運用を誰がどれくらいの分量で分担するかを考慮して決めることです。セラーの場合は、出品から販売、配送に至るまでの業務の大半を販売者が行う必要がありますが、自由度が高く自分のブランドイメージを反映しやすい特徴があります。
ベンダーで取引する場合は、これらの業務をAmazonに任せることができ、特に販促や在庫管理の負担が軽減されます。しかし、施策や販売価格をAmazonにゆだねるため、売上が高くない場合は期待するほどのサポートが得られない可能性もあります。
売上規模とポテンシャル
ベンダーとして出品する一つの基準に、取引金額があります。最低でも年間1億円程度の売上がないとベンダーマネージャーとの交渉が始まらないと推測されています。カテゴリーによって基準は異なりますが、大きなカテゴリー(例:家電)では年間10億円以上の売上が必要になることもあります。
逆に、成長中のカテゴリー(例:ファッション)では年間1億円程度でも担当者面談が行われることがあります。ベンダーの場合、送料をAmazonが負担してくれるため、特に2000円以下の商品ではベンダーの方が有利になることが多いです。
6. 成功に向けた戦略的アプローチ
現状と課題の把握
現在のAmazon市場では、セラーとベンダーそれぞれに特有の課題が存在します。セラーは競争の激化により差別化が困難になっており、広告費の高騰やカートボックス獲得競争の激化により、収益性の確保が課題となっています。
ベンダーは、Amazonが仕入れ量を制限する傾向が強まっており、価格交渉や在庫管理が困難になっています。期待されるプロモーション活動が十分に実施されないケースも増加しています。
ハイブリッド戦略の検討
近年は、ベンダーとセラーの両方を活用するハイブリッド戦略を採用する企業が増加しています。主力商品はベンダーで安定供給を確保し、新商品や特殊商品はセラーで柔軟に対応するアプローチです。
この戦略により、ベンダーとしての安定した卸売りと、セラーとしての自由な価格設定と直接販売の利点を組み合わせることができます。また、ベンダーでは価格のコントロールができないデメリットを、セラーでの直接販売で補うことも可能です。
成功の鍵
どちらの形態を選択する場合も、継続的な改善施策の実行と、Amazon市場の変化に対応する柔軟性が成功の鍵となります。商品ポートフォリオ全体を考慮して、セラービジネスかベンダービジネスのどちらが自社に適しているかを判断することが重要です。
自社の事業特性と市場環境を総合的に検討し、最適な出品戦略を構築することで、Amazon市場での成功を実現できるでしょう。特に、データ分析に基づく継続的な改善と、顧客ニーズに対応した柔軟な戦略変更が、長期的な競争優位性の確保につながります。

監修者 : 田中 謙伍
株式会社GROOVE 代表取締役
慶應義塾大学環境情報学部卒業後、新卒採用第1期生としてアマゾンジャパン合同会社に入社。出品サービス事業部にて2年間のトップセールス、マーケティングマネージャーとしてAmazon CPC広告スポンサープロダクトの立ち上げを経験。株式会社GROOVEおよび Amazon D2Cメーカーの株式会社AINEXTを創業。立ち上げ6年で2社合計年商50億円を達成。
【登録者数 5万人のYouTubeチャンネル】
たなけんのEC大学:https://www.youtube.com/@ec8531

執筆者 : 松岡 孝明
株式会社GROOVE マーケティング事業部
大学卒業後、大手百貨店に就職。店頭での販売やマーケティング経験を積んだ後、ECコンサルティング事業を行なう企業へ転職。現在は株式会社GROOVEにて、マーケティングを担当。EC運営に関するお役立ち情報の発信や、セミナーの企画などを行なっています。