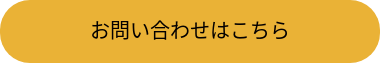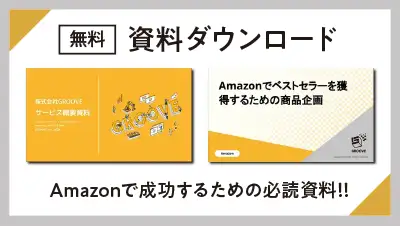EC事業を「情報発信+機会創出」として活用。 伝統工芸の担い手が生み出した独自のスタイルとは?
株式会社山家漆器店 様

写真:株式会社山家漆器店 代表取締役 山家 優一 様
株式会社山家漆器店様は、和歌山県海南市で生産され、日本の三大漆器のひとつである「紀州漆器」を製造・販売されている企業です。
伝統工芸の会社としては珍しく先代である会長が自社ECサイトを2000年に開設、その後もECモールでの販売を開始し、山家社長が2016年に山家漆器店に戻り、さらにEC販売を強化。中でもAmazonでは、2021年に 出品者アワードを受賞されています。
四代目である山家社長は、自社のECによる事業展開だけでなく「漆器で遊ぶ。(Playing with lacquerware.)」をコンセプトに、BtoB / BtoCといったビジネスの領域を越えて、漆器という伝統文化の魅力を発信しています。
今回のインタビューでは、そんな山家社長にGROOVEとの出会いから、独自の仕事観、そして未来への展望についてお話を伺いました。
ECを活用して「継承した家業を成長させる」という観点だけでなく、ECのメリットを活かした「情報発信+機会創出」という独自のスタイルについても、貴重なお話をお聞きすることができました。ぜひご覧ください。
意外な契機:海外から家業を見た時に気付いたECの可能性
- まずは山家漆器店様がEC事業を始められたきっかけを教えてください。
当社では2000年に自社ECサイトを立ち上げて、オンラインでの販売をスタートさせました。今でこそ、多くの伝統工芸の産地が、ECでの販売を行っていますが、当時としてはかなり早い段階での取り組みだったと思います。
その後、2009年からは楽天市場などECモールへの出店も開始して、Amazonには2012年に出店しました。とは言え社内にECの専任スタッフを置いていた訳ではないので、積極的に事業として展開していたわけではありませんでした。
実は私自身も、大学卒業後にそのまま家業を継いだのではなく、サラリーマンとして就職し、ミャンマーに海外駐在していました。その時期にあるきっかけがあって、2016年に帰国し、ビジネスとして家業に関わることになったのです。
- ビジネスとして家業に関わることになった「きっかけ」とはなんでしょうか?
ミャンマーにいた時に、正直なところ暇つぶし程度の気持ちで、家業のECサイトやECモールにログインしてみたのです。もちろん積極的に取り組んでいなかったので、当時はあまり売れていなかったのですが、自分で調べながら、色々と試したところ、意外なほどに売上が伸びていったのです。
すぐに「これは面白い!」と感じて、さらに手を入れて売上を伸ばし、家業であっても自分の給料分は稼げるくらいの目途を立てた状態にしてから、和歌山へ戻り本格的に「漆器 ✕ EC」を動かし始めました。
またミャンマー駐在時には、家業の商品を手土産に持って行くことが何度かあったのですが、みなさんとても喜んでくださり、どんな素材なのか?、どうしてこんなに美しいのか?と大変興味を持っていただきました。
しかし日本に戻ると「漆器はもうアカン」という声を聞くことの方が多く、とても疑問に感じていました。ひょっとして「アカン」と思っているのは業界の人だけで、漆器という伝統工芸そのものや、中でも「紀州漆器」だからこそできる何かが、まだまだ沢山あるのではと考えるようになりました。

- 「紀州漆器」だからこそできる何か?とは具体的にどんなことでしょうか。
漆器業界のEC化についてお話すると、実は紀州漆器が一番ECに積極的に取り組んでいます。紀州漆器とともに、三大漆器と呼ばれる輪島塗(石川)や、会津塗(福島)は、いずれも高級品としてブランド力があるので、ECで直販するとなると、百貨店などオフラインのしがらみも多い。その点で紀州漆器は、お盆やお椀、弁当箱やお箸など日常生活の道具として親しまれているので、ECに参入しやすかった、という背景があります。
また、紀州漆器は新たな技術を取り入れることに柔軟な姿勢が特徴で、扱う素材についても、木に限らず、プラスチックやガラス、金属など、積極的にチャレンジしている産地です。そのため新しいニーズに対する対応力が高い点も、ECでの商品企画・開発に向いているかと思います。
ECでは低価格帯から中価格帯の商品が良く売れる傾向があるので、手頃な価格で普段使いできる商品には、明確な存在価値があると考えています。自動車でも高級車だけが「良い車」であれば、乗れる人が限られてしまいますよね。それに対してコンパクトカーや軽自動車という存在があるからこそ、車という便利な生活インフラをより多くの人が利用できる。
こうした考えで、山家漆器店として、また紀州漆器としても、やれることは何でもやろう!というマインドで取り組んでいます。

独自の仕事観:伝統工芸にこそ必要なポジティブマインド
- SNSを拝見すると、製造・販売以外にも、本当に様々なアクションをされていますね。これはどういった想いで行っているのでしょうか?
伝統工芸でよく言われる「文化として育てる」という言葉は、私にとって「頑なに昔ながらの製法を守り続けること」ではないと思っています。
例えば、大学生が地方から上京して、一人暮らしの食器を揃えるときに、「やっぱり味噌汁はお椀で飲みたいな」と考えたとします。この「やっぱり」という感覚は、実家で昔から漆器のお椀を使っていた経験や、旅館で出会った美しい絵柄の漆器など、色々な記憶の中から生まれると思うのです。
その感覚を頼りに、実際に漆器の椀を探すと、高級品から100円ショップの商品まで色々出てくるのです。普通の漆器業界の人なら「高級品にしておけば、一生使えるよ」と言いたくなるのですが、私は「まずは100円ショップのお椀でも全然かまわない。」と思っているんですね。
とにかく「自分で買った漆器のお椀」が一つあれば、いつか自分でお金を稼いでゆとりができたとき、また家庭を持ったときに、その時の暮らしに合った新しい漆器に出会ってもらえればそれで良いんです。
文化として育てるというのは、無理に押し付けるものではなく、心に残って、体験として繋ぎ続けることだと思っています。特にECだと、100円のお椀も、1万円のお椀も、検索すると全部出てきてしまう。それをネガティブに捉えるのではなく、そもそも「お椀」として「検索され続ける」ことが大切なのです。
- 普通は自社の事業をどう伸ばすか?が最優先だと思いますが、どこからそうした考え方が生まれたのでしょうか?
私は職人として工房に入ることはないので、積極的に外へ出るようにしています。もっと言えば、私は会社にいるよりも、外にいた方が会社の売上が上がると考えているので。
そんな考えだからなのか、おかげさまで、色々な方と出会う機会が多く、「漆器」というキーワードで色々な話が舞い込んでくるようになりました。その中には、もちろん自社で対応できない相談もあるのですが、私はそこで断らないんです。
産地の仲間の中から、時には産地の枠も超えて、その相談に応えられる人を紹介するようにしています。イメージとしては「紀州漆器ホールディングス」という感じですね。漆器について「知りたい、試したい、作りたい」方の窓口になれたら良いと考えています。
- 紀州漆器そのものをプロデュースしている状態ですね。
そんな大げさなものではないですが「断らない姿勢」は大切にしています。
最近では、2025年に開催される大阪・関西万博の和歌山パビリオンでの案件に関わりまし た。高さが4mもある映像タワーの筐体を漆器の技術で仕上げる、というものだったのです が、自社だけでは出来なかったことも、私が組合メンバーを繋ぎ、各社の得意分野を集結させることでいよいよ実現が見えてきています。
他にも全国から「漆器の技法でこんなものを作れないか?」という相談をいただくことがあるですが、こうした相談は普通の工房なら断ってしまうことが多いようです。でも私は全部チャンスに変えられると思っています。そうした相談から生まれた新しい商品を、先方にきちんと相談した上で自社でも販売してみて、売れるようなら定番化する、といったアクションも行っています。
- 新しいアクションがしっかりと自社の利益にもつながっているのですね。
もちろん全てが売上や利益につながっているかと言えば、そうではありません。
例えば、イベントへの出店も色々と声をかけていただくのですが、売上だけで見たら、正直なところ参加するのは中々難しいと感じます。しかし、私にとってイベントは単なる販売機会でなく、当社のフォロワーさんと直接お会いする貴重な機会なのです。そこでの出会いを、例えばSNSに投稿することで、それは私たちにしか作れない新しい価値になります。
オンラインで売って、オフラインでも繋がっていく。こうしたアクションは、大手さんとの差別化としても有効で、小さい会社だからこその勝ち方のひとつだと思います。他の伝統工芸でも「魅せる仕事」は得意だけれど「売る仕事」が全然できていない、といったケースや、その逆も良く耳にします。私としては、どちらかに極端に寄せたり、無理に分けたりしても、成長できないと思います。
常に利益だけを追うのではなく、ECでしっかりと数字を作りながら、顧客とどのようにコミュニケーションを図って行くのか、これをしっかりと考えたいですね。
GROOVEとの出会い:突然の訪問から生まれた絆
- 山家漆器店様とGROOVEとの出会いはどのような形だったのでしょうか。
これは中々面白いエピソードでして、GROOVEの田中社長が和歌山にある当社へ、アポなし訪問されたのがきっかけなんです。その日は会社が休みの土曜日だったのですが、たまたま納品の関係で私が会社にいたのです。話を聞いてみたところ、当時から田中社長が運営しているYouTubeチャンネル「たなけんのEC大学」に出演してくれませんか?というお誘いでした。
きっかけは2021年に当社が Amazonで「Amazon出品者アワード2021 -ご当地の魅力 発信賞- 」を受賞したことだったようですが、GROOVEが掲げている「日本のモノづくりをアップデート」テーマに、山家漆器店のアクションがマッチしていたから、出演のオファーをいただけたんだと思います。
※山家社長に出演いただいた動画はこちら 前編 / 中編 / 後編
YouTubeへ出演した後に、EC支援のサービスもぜひ!と声をかけてくれたのですが、当時はまだモール運用を外注するほどの売上ではなかったので、正直どうしようかな、と迷っていました。
しかし、外部パートナーを活用することで、Amazonでのビジネスをどれだけスケールできるのか?ということに興味もあったので、思い切ってお願いすることにしました。それが2022年10月のことなので、もう丸2年以上のお付き合いですね。
- GROOVEによるAmazon運用は、貴社にどのような価値を提供できているでしょうか。
価値と言われると、一番はやはり売上ですね。契約前に比べて、ほとんどの月で2.5倍くらいの売上になっています。GROOVEによる広告運用の成果だと思いますが、同時に、EC業界全体で言えば、楽天市場が伸び悩みの傾向にある中で、Amazonはまだまだ伸びてきているなと感じています。
当社では楽天の方が早くから取り組んでいるので、これまでは常に楽天の売上がAmazonを上回っていたのですが、ここ最近は楽天の売上をAmazonが上回ることが増えてきました。
利益という観点でも、当社はメーカーであり、販売会社でもあるので、適切な広告運用を行って販売個数を伸ばすことは、メーカー視点で言えば利益が出ていることになります。この部分をしっかりと切り分けて、利益をしっかり見ながら回して行くことも大切なポイントだと思っています。
- 他にもGROOVEとの伴走から得られた良いインプットはありますか?
良いインプットは?と聞かれたら、それは商品提案ですね。Amazonでのレビューや競合分析をもとに、GROOVEが提供してくれる商品企画のアイデアは、Amazonに限らず当社のEC事業全体に貢献していると思います。
具体的には、お椀とお箸のセットとか、ラッピングやロゴ入れによる差別化など、色々なアイデアをくれます。そのアイデアをまずはAmazonで試して、売上が伸びるものは、そのまま楽天市場も含めた他のECにも展開しています。
- 商品企画の話がでましたが、Amazonでのヒット商品といえばどんなものがあるでしょうか?
ひとつは「曲げわっぱ 弁当箱」ですね。Amazonで「曲げわっぱ」で検索すると、低価格帯から高価格帯まで沢山の商品が表示されます。低価格帯は主に「器は海外製、塗りは国内で」という商品なのですが、当社の場合は「器も塗りも全て国産」という商品を中価格帯で送りだしたらどうなるか?と考えて商品化しました。
データを元にしたマーケットインからスタートし、プロダクトアウトで付加価値を付けた、ECならではの商品企画事例だと思います。おかげさまで、今でも当社の人気商品ですね。
もうひとつは「半月盆」です。これは紀州漆器にとって、もう何十年も前からある定番商品なのですが、当社が一番沢山販売していると思います。こうした産地としての代表的な商品も、見せ方や伝え方の工夫で、より多くのお客様の手に取っていただけるようにできるのは、Amazonならではだと思っています。
GROOVEには、こうした人気商品をさらに伸ばす方法から、ストアページやA+での見せ方など、独自の知見を活かしたサポートを幅広く提供してもらっています。
- Amazonでの販売実績は、ビジネス全体にどのような影響を与えましたか?
Amazonで一番売れている!とお話した半月盆ですが、イベントに参加した際に、お客様から「山家さんですよね! 私、山家さんの半月盆を使ってます!」と声をかけていただいたことがあります。
こうしたブランド認知の効果も含めると、Amazonでのアクションは単なる売上だけで測れないものがあります。販売個数が増えるということは、そのまま「使っていただける人が増える」に繋がり、さらに気に入っていただけたら、また「山家漆器店から」買っていただける可能性が広がる。こうした考え方を持っていないと、今のECでは生き残れないと感じています。
要は目の前の数字だけで勝負したり、判断するのはしんどいと思うのです。ECで販売個数や売上・利益といった数字をしっかりを出しながら、オフラインでも、そしてSNSなどのオンラインでも、顧客とどのように繋がっていけるかを常に考えています。
売上規模がまだ大きくない状態で、当面の利益だけを考えると、GROOVEのようなパートナーに支援を依頼する余地はないかも知れないですが、当社の場合は思い切ってプロの知見を活かしたことで、しっかりと数字を作ることができました。おかげさまで、今では次の景色が見えてきたかな、と感じています。
EC運用でパートナーを活用するメリットは他にもあります。前述の通り、私は出来るだけ会社にいない方が、ビジネスを拡大できると思っていて、新しい出会いや情報やアイデアを得られるように動いています。Amazonの運用をある程度、信頼して任せられることで、そうした出会いの時間を増やすことに繋がっていますね。やはり餅は餅屋ってことです。もちろん丸投げは決してしませんが、効果があるならプロを上手に活用することをおすすめします。

未来への展望:「漆器で遊ぶ。」から広がる新たな可能性
- EC事業も含めて、今後はどのような目標を掲げているのでしょうか。
一つは海外での展開ですね。ここ数年、おかげさまで海外での売上が徐々に増えています。同時にAmazon経由での海外からの問い合わせも増えているのです。
具体的な例ですと、フィリピンから「こんな感じの漆器を200個作って欲しいができますか?」という問い合わせがありました。その後、チャットでやり取りを続けて、最終的には200万近い売上の案件にすることができたのです。
先方は当初、日本の企業に何社か同じ問い合わせをしたそうなのですが「返事をくれたのは山家さんだけだった」と後から教えてくれました。ECプラットフォーム上での海外販売も、しっかりと準備を進めて伸ばしていきたいですが、山家漆器店としては、こうした問い合わせからの取引も、一つの越境ECだと思っているので「漆器のことなら、山家漆器店に聞けば返事が返ってくるよ!」と言ってもらえるようにしたいです。
他にも、海外の展示会に出展した際のおもしろいエピソードがあります。山家漆器店として出展したSTYLE BANGKOKというタイの展示会は、人も疎らだったので、具体的な商談には繋がらなかったのですが、期間中に知人を介してすばらしい機会が得られました。
なんと現地のミシュラン星付きレストランで、和歌山の食と山家漆器店のコラボイベントを開催することができたのです。もう私としては展示会よりも完全にこちらがメインで、良い写真も沢山撮れて、新しいつながりも生まれました。いま振り返っても、大きな収穫だったと思います。

バンコクのミシュラン掲載店テロワールでの「Special WAKAYAMA Dinner」の様子。写真提供:山家漆器店
- EC事業だけで考えるのではなく、ビジネス全体の広がりを重視しているのですね。
はい。ECでは転換率を高めることが重要なKPIですよね。これをテクニカルな要素だけで改善するのでなく「山家漆器を知っている」というブランド認知も活用して高めていくことが、ビジネス全体の売上につながってくると考えています。
具体的には「曲げわっぱの弁当箱が欲しい!という人に対して、価格戦略や、広告運用よりも、「山家漆器店の曲げわっぱを買う!」となってくれることが、最終的には一番強いと思うのです。
ですので、正直なところ「Amazonで何億の売上をつくる」といったことは、当社としてのゴールではないと思っています。もちろん数字は大切で、利益を出しているからこそ、新しいアクションもできるのですが、常に「漆器で遊ぶ。」という言葉に軸足を置いて、国内に限らず海外も視野に入れた「山家漆器にしかできないアクション」から利益を出せるようにしたい。
なぜならAmazonでの売上は、やはりどこかで「パイの取り合い」なので、山家漆器店がそこにいなくても、誰かがそれを取っている。しかし、フィリピンのような事例は、当社が返事をしなかったら、その商品は存在しなかった。こうしたアクションの方が価値があると思っていますし、こうした新しいアクション自体が「漆器で遊ぶ」という意味だと捉えています。
バンコクのミシュラン星付きレストランでのコラボイベントも然りで、商品は真似されても、リアルなつながりから生まれるアクションは、真似されることがないですよね。正に海外でも「漆器で遊ぶ。」を具現化しながら、世界各国に商品だけを送り届けるのではなく、各国に1社で良いから、本当に繋がっているコネクションを、ひとつひとつ作っていきたいと考えています。
編集後記:「利益と認知」をECで育て、次なる挑戦につなげる
今回のインタビューでは「ECを活用して利益を出す」ことが、「ブランドとしての認知拡大」に必要な新しいアクションの前提条件となっていました。
GROOVEが、その前提条件である「利益の創出」に貢献できていることに喜びを感じると同時に、次なる挑戦の領域にも、パートナーとして関わり続けたいと強く感じました。そのためにはGROOVEでも、新たなサービスメニューの開発を進めて、ECを軸とした事業戦略をトータルにサポートしていきたいと考えています。
インタビュー中に「Amazonというプラットフォームを使って、紀州漆器で面を取って、ブランド認知を高めていきたい」という言葉がありました。正にこれから必要となるECプラットフォームの活用方法だと思います。
山家漆器店様のように、ECプラットフォームを単なる売場ではなく、事業全体を押し上げるために活用したい、と考えている事業者の方は、ぜひGROOVEまでご相談ください。最新の事例と手法をご案内させていただきます。