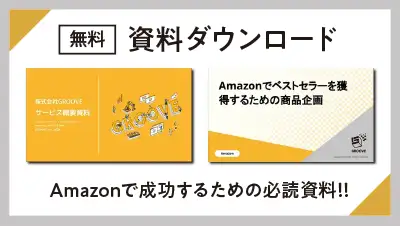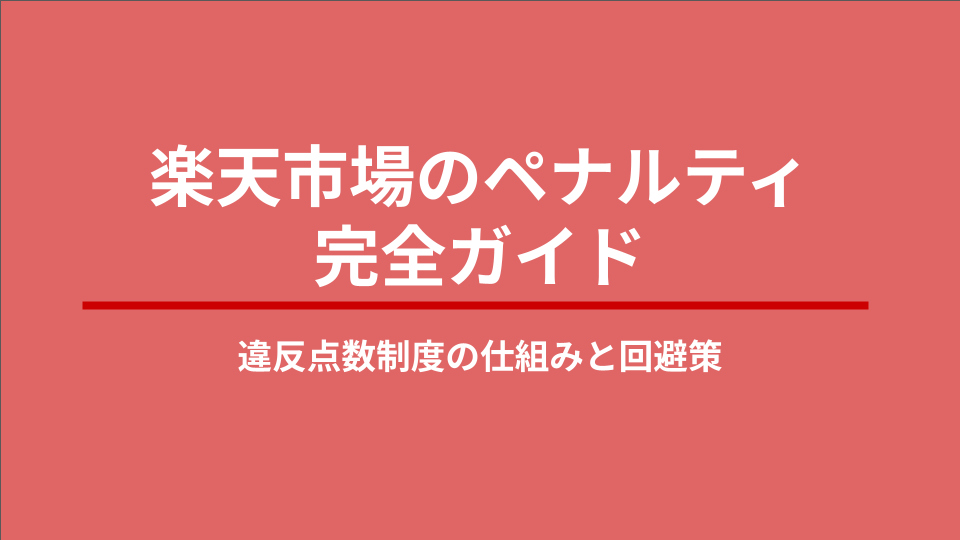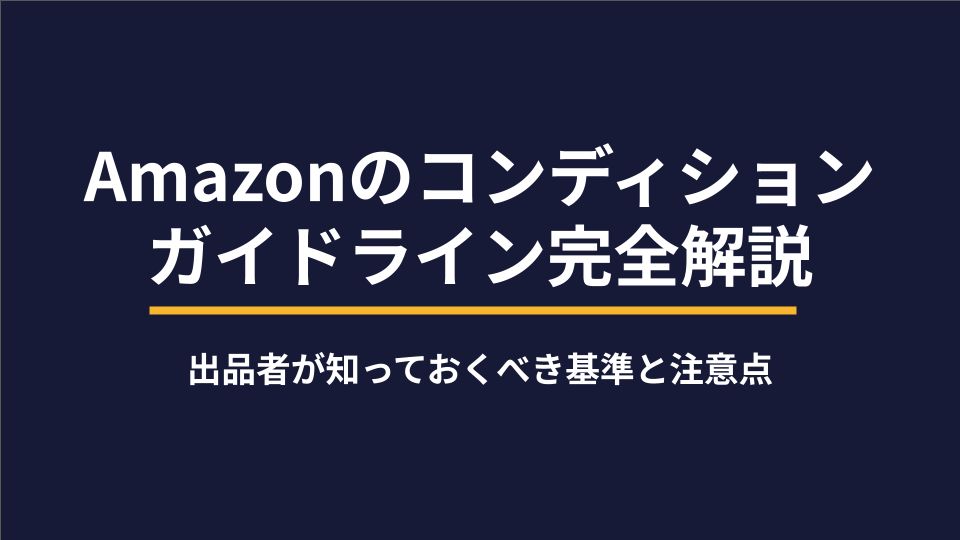Amazonのブランドストア(ストアページ)は作るだけで終わるべきではない!ストアを有効に活用する戦略的運用術
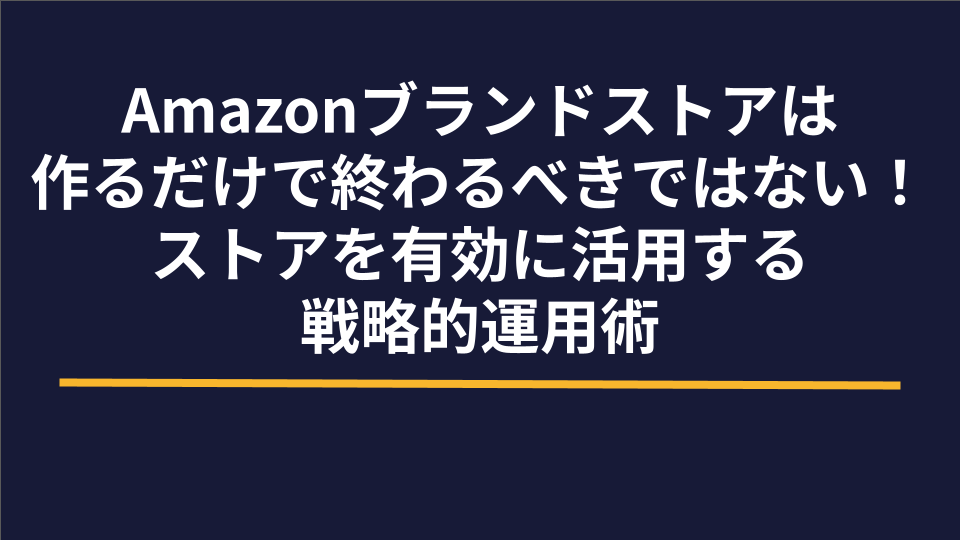
Amazonでの売上拡大を目指すメーカーにとって、ブランドストアの活用は今や必須の戦略となっています。通常の商品ページだけでは伝えきれないブランドの魅力や価値を効果的に表現し、競合他社との差別化を図ることができるAmazonブランドストアは、売上向上とブランド力強化の両方を実現する強力なツールです。
しかし、単にブランドストアを作成するだけでは十分な効果は期待できません。戦略的な設計、効果的な運用、継続的な改善を通じて、はじめてその真の価値を発揮することができます。本記事では、Amazonブランドストアを最大限に活用するための具体的な方法論を、基本概念から実践的な運用テクニックまで体系的に解説します。
ブランドストアの構築を検討している方はもちろん、既に運用中だがさらなる成果向上を目指している方にとっても、実践的で価値のある情報を提供いたします。データ分析に基づいた改善方法から外部メディアとの連携戦略まで、成功に必要な要素を包括的にカバーしていますので、ぜひ最後までご覧ください。
1. Amazonブランドストアとは何か
Amazonブランドストアは、Amazon内に常設できる自社専用のブランドページです。通常のAmazonの商品ページがシンプルな作りであるのに対し、ブランドストアでは商品やサービスを検討しているユーザーに対して、ブランドの魅力や価値を十分に伝えることが可能となっています。
従来の商品ページでは、主に商品ごとの紹介を行う作りとなっており、ブランドそのものの魅力を表現することが困難でした。しかし、Amazonブランドストアを活用することで、商品ページでは伝えきれなかった自社ブランドの魅力やこだわりを、視覚的かつ効果的に伝達できるようになります。
このプラットフォームは、商品一覧や特集コンテンツ、セール情報など、様々なプロモーションを展開することができる多機能な環境を提供しています。ブランド登録済みの出品者であれば誰でも無料で作成できるため、中小企業から大企業まで幅広い事業者が活用できる現実的な選択肢となっています。
Amazon市場における競争が激化する中で、単なる商品販売ではなく、ブランド価値を明確に伝達し、顧客との深い関係性を構築することが求められています。ブランドストアは、このような現代のEC戦略において欠かせない重要なツールとして位置づけられています。
2. ブランドストア活用によって得られる5つの主要メリット
ブランディング力の大幅な強化
ブランドストアの最大の価値は、強力なブランディング効果にあります。商品ページとは異なり、自社ブランドのイメージに合わせてコンテンツ内容を独自にカスタマイズできる仕様になっているため、ブランドカラーやロゴを自由に取り入れ、一貫したブランドイメージを訪問者に伝えることができます。
Amazon上には数多くのブランドが存在し、その中でユーザーから選んでもらえるような差別化を図るためには、印象的で記憶に残るブランド体験の提供が不可欠です。自由なレイアウトでブランドや商品のイメージを伝えることができるブランドストアは、市場競争に勝つための有効な手段となります。
クロスセルとアップセルの効果的な促進
ブランドストアでは、クロスセルやアップセルを実施し、顧客単価の向上や顧客満足度の向上につなげられる大きなメリットがあります。商品ページでは簡易的な商品説明しかできず、同ページに競合商品がレコメンドや広告で掲載されることがありますが、ブランドストアは自社ブランドのみの商品掲載ができるため、他の商品のクロスセルやアップセルの促進が可能です。
複数のページを作成し、ページ内を回遊させることにより併売を促すことも可能となっています。機能やデザインの違いが多く、ユーザーがどれを選択すべきか悩みやすい商品を扱っている場合は、ブランドストア内で商品比較やそれぞれの特徴を説明することで、購買決定を支援できます。
包括的なユーザー動向分析の実現
ブランドストアには、ストアインサイト機能が搭載されており、詳細なユーザーの動向を分析できる強力なメリットがあります。商品ページでは流入元や売上などの詳細なデータ分析を行うことができないのに対し、日別の訪問者数、日別の閲覧数、ストアページ経由の売上金額、ストアページ経由の売上件数、トラフィック参照元などのデータを細かく分析できます。
これらのデータは全て日別またはページ毎に確認可能であり、売れやすい時期や訪問者数が増えるタイミングを正確に分析することができます。このような詳細な分析結果を活用して、より効果的な戦略立案と実行が可能となります。
広告との戦略的連携による集客力向上
ブランドストアは、Amazon内外の様々な広告から直接ブランドストアへ顧客を誘導できる柔軟性を持っています。Amazon内広告であれば、スポンサーブランド広告でストアページを遷移先に設定することで、ブランディング強化につながります。Amazon外広告であれば、GoogleやYahoo! JAPANなどの検索エンジン広告の遷移先として、ブランドストアを設定可能です。
さらに、InstagramやFacebookなどのSNSの広告出稿時にも、ブランドストアを遷移先として設定できます。この機能によってAmazon内外の広告からブランドストアへ顧客を誘導し、ブランド認知度やブランド理解の促進につなげることができます。
コスト効率の高い運営環境
ブランドストアは、無料のテンプレートが使えるため、Webページ作成のスキルがなくても安心して利用できます。用意されたテンプレートに沿ってテキストや画像を設定するだけで、短時間でブランドストアを作成することも可能です。また、掲載順や配置も自由にカスタマイズできるため、経験や知識がなくても質の高いブランドストアを作成できる環境が整っています。
3. ブランドストア作成に必要な準備と条件
大口出品プランへの登録
ブランドストアを作成するためには、まず大口出品プランへの登録が必要となります。Amazonの出品プランには大口出品と小口出品があり、大口出品は販売数に限らず月額4,900円(税抜)、小口出品は商品1点を販売ごとに100円の手数料が発生する仕組みとなっています。
大口出品プランに切り替えることで、ブランドストアの登録に加えて、ビジネスレポート等の各種レポートが取得できる、Amazonカートボックス獲得の条件を満たせる、在庫ファイルを使った商品登録ができる、配送料を設定できる、商品ごとの利用料が発生しない、商品にプライムマークが付与できるなどの多くのメリットも享受できます。
プラン切り替えは、Amazonセラーセントラルにアクセスし、設定メニューから出品者アカウント情報を選択、ご利用のサービスの右側に表示されるサービスの管理を選択、Amazon出品サービスのセクション内で大口出品に変更を選択することで実行できます。
Amazonブランド登録の実施
Amazonブランド登録は、Amazon上において自社のブランドを保護し、管理強化するためのプログラムです。この登録は無料で実施できるものの、事前に登録保留中または有効な文字商標、図形商標などが必要となります。商標登録には数か月から1年ほどかかるため、ブランドストアを検討している場合は早めの手続きが重要です。
ブランド登録には、ブランドストアの利用だけでなく、商品ページの書き換え防止、偽造品や模倣品の摘発、ブランドの認知向上、Aプラスコンテンツの作成などの付加的なメリットもあります。申請から審査終了までの期間は約1〜2週間ですが、提出不備があるなどの理由で登録が却下された場合は、再申請が必要となる可能性もあるため、時間に余裕を持って登録を行うことが推奨されます。
4. 効果的なブランドストア構築のステップ
セラーセントラルでの基本設定
ブランドストア構築の最初のステップは、Amazonセラーセントラルへのログインです。Amazonセラーセントラルは、Amazonで商品を販売するための管理画面であり、ブランドストア作成の起点となります。ログイン後は、上部にある「Amazonストア」を選び、ストア作成のボタンを選択します。
画面遷移後はストア作成のボタンをクリックし、ブランド名とブランドロゴを設定します。ブランドロゴはAmazonのガイドラインを遵守する必要があるため、公式サイトのルールを事前に確認しておくことが重要です。ブランドロゴに設定できる画像のサイズは「400×400px」と定められているため、画像のサイズにも注意が必要です。
メタディスクリプションとコンテンツ設計
ページのメタディスクリプション欄には、ページコンテンツの概要を入力します。作成中のページやブランドについての説明文を入れることで、検索エンジンからの評価向上も期待できます。この段階では、ブランドの核となる価値提案を明確に表現することが重要です。
基本設定が完了したら、次はテンプレートやページセクションを追加します。複数のテンプレートが用意されているため、ブランドや商品のイメージに合うものを慎重に選択しましょう。コンテンツを作成するためには、テンプレートに配置されているコンテンツを編集するか、新しいコンテンツを追加します。
高品質なコンテンツの制作
追加できるコンテンツには、画像、テキスト付き画像、テキスト動画、おすすめ商品などがあります。ページ内のコンテンツはブランドストア全体のクオリティに直接関わる部分であるため、十分な時間をかけて工夫することが成功の鍵となります。
コンテンツ制作においては、ユーザーの購買行動を意識した構成を心がけることが重要です。ブランドの世界観を表現しながらも、実用的な商品情報を適切に配置し、購買に至るまでの導線を明確に設計する必要があります。
審査プロセスの対応
ブランドストアを作成したら、Amazonによる審査プロセスを経て公開となります。審査では、Amazonガイドラインに違反する項目がないかをチェックされ、違反がある場合は審査に通りません。この場合は再審査が必要となって時間も多くかかるため、審査に出す前にガイドラインに準拠しているかどうか確認しておくことが必要です。
5. 売上向上につながる運用戦略
戦略的な広告連携の実装
ブランドストアを成功させるためには、広告との連携が極めて重要なポイントになります。広告戦略を立てる際には、ブランドストア内で売れている商品や売り出したい商品を整理し、その情報をもとにターゲティングを行います。これによって広告を見た消費者は、ブランドストアにアクセスした際、関連性の高い商品を見つけやすくなります。
スポンサープロダクトなどの広告フォーマットを活用し、ブランドストアと連動させることで、効果的な販促を図ることが可能です。広告運用はブランドストアへの流入を増やすだけでなく、ブランドストア内のセールスに役立てることもできます。効果的に広告とブランドストアを連携するためには、データ分析や広告運用の最適化などが重要な要素となります。
Amazon内SEO対策の徹底
ブランドストアへの自然流入を増やすためには、Amazon内でのSEO対策も重要になります。SEO効果を高めるためには、商品名や商品説明、検索キーワードフィールドなどにキーワードを適切に配置することが重要です。商品のレビュー評価や過去の販売実績がいい商品ほど検索ランキングで上位に表示されやすくなる傾向があります。
FBAを利用してprimeマークを獲得することで、検索結果での優位性を高めることも可能です。在庫切れを避け、検索結果に常に表示されるようにすることがポイントになります。継続的なキーワード分析と最適化により、長期的な集客力向上を実現できます。
A+コンテンツとの効果的な連携
ブランドストアを成功させるためには、商品紹介とA+コンテンツを効果的に活用することが不可欠です。A+コンテンツは、画像、テキスト、比較表などを追加し、商品の魅力や特徴を効果的に伝える機能です。商品に関する詳細な情報、ストーリーをさまざまな方法で表現できるため、消費者により深い興味を持ってもらうことができます。
A+コンテンツ内にブランドストアへのリンクを設置し、個別商品ページからブランドストア全体に誘導させることができます。一方で、ブランドストアの商品ページからA+コンテンツに誘導することも可能です。A+コンテンツを充実させることはブランドストアを魅力的にすることにつながるため、それぞれを効果的に活用することが重要です。
6. データ分析を活用した継続的改善方法
ストアインサイトの活用法
ブランドストアの成功には、ストアインサイト機能を活用した継続的な分析と改善が欠かせません。この機能を通じて、ユーザーはどのページをよく見る傾向にあるか、訪問者数や回遊率はどのように推移しているかなどユーザーの動向を詳細に分析できます。これらの分析結果に基づいて、ページ構成やバナーの改修を継続的に行うことで、より効果的な売上増加を狙うことができます。
データ分析においては、単なる数値の把握にとどまらず、ユーザー行動の背景にある心理や動機を理解することが重要です。例えば、特定のページでの離脱率が高い場合、そのページのコンテンツや構成に改善の余地があることを示唆しています。
定期的な最適化の実施
ブランドストアは、定期的に更新して最適化を図ることが重要です。最適化を図ることによって、顧客の再訪率が向上したり、売上の増加につながったりなどのメリットがあります。最適化の方法として、新商品の追加、コンテンツの刷新、季節やイベントに合わせた更新、データに基づく改善などが挙げられます。
ブランドストアは90日程度を目安に、必要に応じて更新していくのが効果的です。また、主要なイベントやセールが行われる場合は、その都度コンテンツをチェックし、必要に応じて更新することも重要です。継続的な改善により、競合他社との差別化を維持し、顧客満足度の向上を実現できます。
課題特定と対策の体系化
ブランドストアで売上を増やすためには、ストアが抱える課題の特定や対策が必要です。インサイトから得られる消費者情報、ストア動向を確認し、データドリブンな改善を行います。例えば、閲覧数が増えているにも関わらず、売上が増えていない場合は、商品の魅力が伝わっていない可能性があります。このような場合は、コンテンツの見直しが施策として有効です。
課題特定においては、定量的なデータと定性的な観察を組み合わせることが重要です。数値だけでは見えないユーザーの体験品質や感情的な反応も考慮に入れて、総合的な改善策を立案する必要があります。
7. 外部連携による集客力強化
マルチプラットフォーム戦略の実装
ブランドストアの集客力を最大化するためには、外部メディアとの連携が重要な戦略となります。外部メディアからの広告遷移先にブランドストアを設定することで、Google、Yahoo!、X、Instagram、Facebookなどのメディアを活用してブランドや商品の宣伝を行い、ブランドストアに誘導することが可能になります。
これらの外部プラットフォームは、それぞれ異なるユーザー層を持っているため、多様な顧客層にアプローチすることができます。特に、Amazon外のユーザーを新規顧客として獲得する上で、この外部連携は非常に効果的な手法となります。
パラメータ管理による効果測定
ブランドストアにはパラメータを発行する機能があります。外部広告ごとに発行したパラメータを設置することにより、外部メディア経由のユーザー訪問者数や売上金額などを正確に計測することができます。この機能を活用することで、どの外部メディアが最も効果的であるかを定量的に把握できます。
効果測定の結果を基に、親和性の高いメディアの発見や、投資対効果の高いプラットフォームへのリソース集中を図ることができます。また、新規顧客となるAmazon外ユーザーの獲得状況も詳細に追跡できるため、マーケティング戦略の精度向上に大きく貢献します。
8. 成功に導く実践的なポイントとコツ
ユーザー体験を重視した設計思想
ブランドストア成功の鍵は、常にユーザー体験を中心に据えた設計思想にあります。美しいデザインや豊富なコンテンツも重要ですが、最終的にはユーザーが求める情報に効率的にアクセスでき、購買決定を支援する構造になっているかが成否を分けます。
ユーザージャーニーを詳細に分析し、各段階でのニーズや懸念点を理解した上で、それらに適切に対応するコンテンツとナビゲーションを設計することが重要です。また、モバイル端末での閲覧体験にも十分に配慮し、どのデバイスからアクセスしても快適に利用できる環境を整える必要があります。
競合分析と差別化戦略
成功するブランドストアを構築するためには、競合他社のブランドストアを詳細に分析し、自社の強みを活かした差別化戦略を策定することが不可欠です。競合分析では、コンテンツの質、ユーザー体験、商品の見せ方、価格戦略などを多角的に検証します。
差別化においては、単に異なることを目指すのではなく、顧客にとって真に価値のある独自性を追求することが重要です。自社ブランドの核となる価値提案を明確にし、それを効果的に伝達できるストア設計を心がけることで、持続的な競争優位を築くことができます。
長期的な視点での運営体制構築
ブランドストアの運営は短期的な施策ではなく、長期的なブランド戦略の一環として位置づけることが重要です。継続的な改善と最適化を行うための運営体制を構築し、定期的な効果測定と戦略見直しを実施する仕組みを整える必要があります。
また、季節性のある商品やトレンドに敏感な商材を扱う場合は、市場の変化に迅速に対応できる柔軟性も求められます。データに基づいた意思決定を行い、顧客のニーズの変化に合わせてストア運営を進化させることで、長期的な成功を実現できます。
9. まとめ
Amazonブランドストアは、適切に活用することで売上向上とブランド強化の両方を実現できる強力なツールです。しかし、その効果を最大化するためには、戦略的な設計、継続的な運用、データに基づく改善が不可欠です。本記事で紹介した方法論を参考に、自社の特性に合わせたブランドストア運営を実践し、競争優位の確立を目指してください。
よくある質問
Q. ブランドストア(ストアページ)は公開までどのくらい?審査で落ちやすいポイントは?
Q. ブランドストア(ストアページ)で必ず追うべきKPIは?ストアインサイトの見方は?
Q. 外部広告やSNSから amazon ストアページへ送客した効果は計測できますか?
Amazonブランドストアの作成や運用は『株式会社GROOVE』におまかせ!
『株式会社GROOVE』は、Amazonを知り尽くしたコンサルタントが戦略立案から代行運用までお客様のご要望に応じてきめ細かにトータル支援します。
Amazonブランドストアのクリエイティブ改善やストア運用代行、広告運用、SEO対策などさまざまなサービスを提供しています。戦略立案やKPI設計、各種分析、商品企画などのサポートや支援も可能です。
貴社の状況に合わせて、成功に貢献できるご提案をさせていただきます。サービス内容や事例などもご紹介いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

監修者 : 田中 謙伍
株式会社GROOVE 代表取締役
慶應義塾大学環境情報学部卒業後、新卒採用第1期生としてアマゾンジャパン合同会社に入社。出品サービス事業部にて2年間のトップセールス、マーケティングマネージャーとしてAmazon CPC広告スポンサープロダクトの立ち上げを経験。株式会社GROOVEおよび Amazon D2Cメーカーの株式会社AINEXTを創業。立ち上げ6年で2社合計年商50億円を達成。
【登録者数 5万人のYouTubeチャンネル】
たなけんのEC大学:https://www.youtube.com/@ec8531

執筆者 : 松岡 孝明
株式会社GROOVE マーケティング事業部
大学卒業後、大手百貨店に就職。店頭での販売やマーケティング経験を積んだ後、ECコンサルティング事業を行なう企業へ転職。現在は株式会社GROOVEにて、マーケティングを担当。EC運営に関するお役立ち情報の発信や、セミナーの企画などを行なっています。